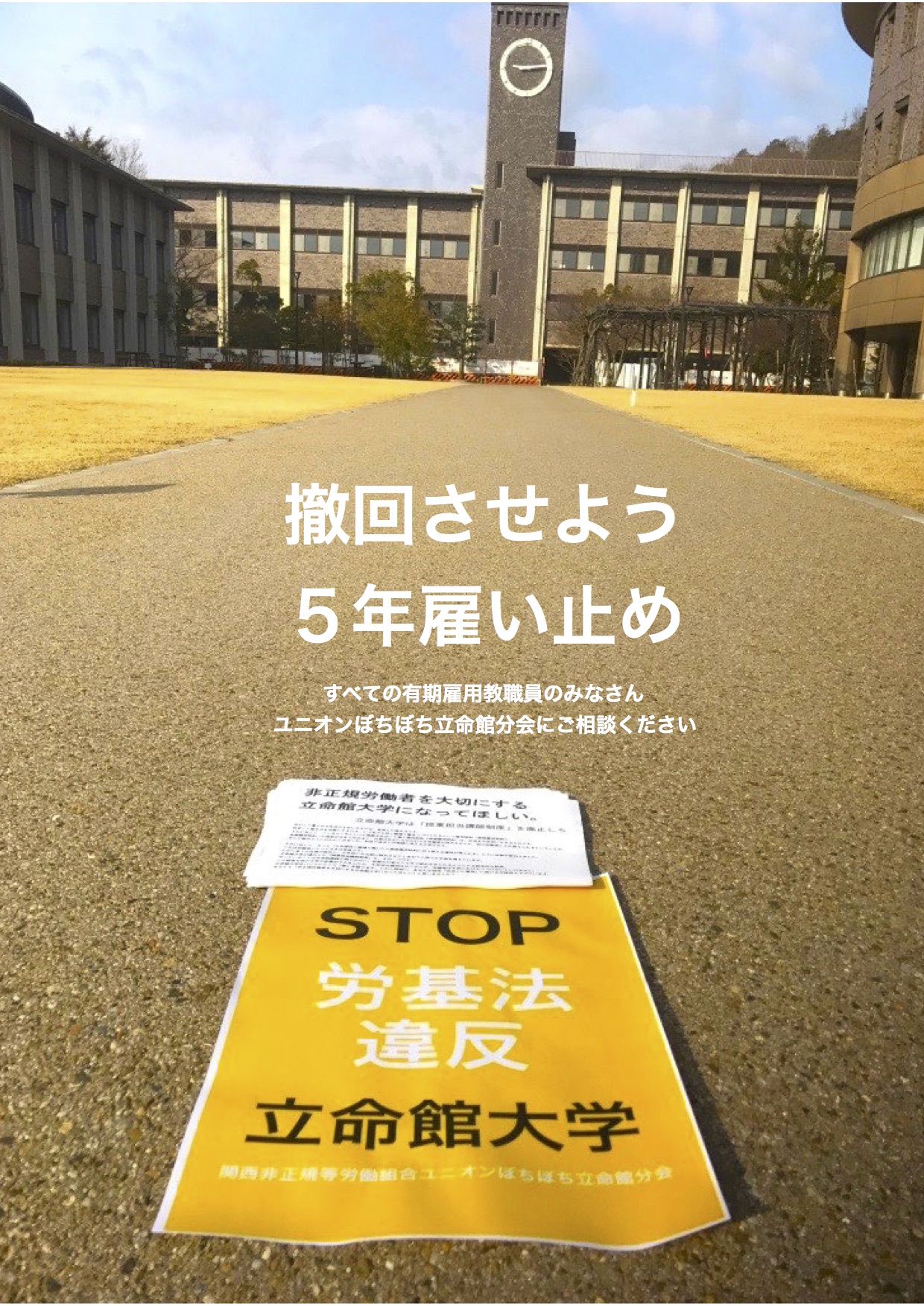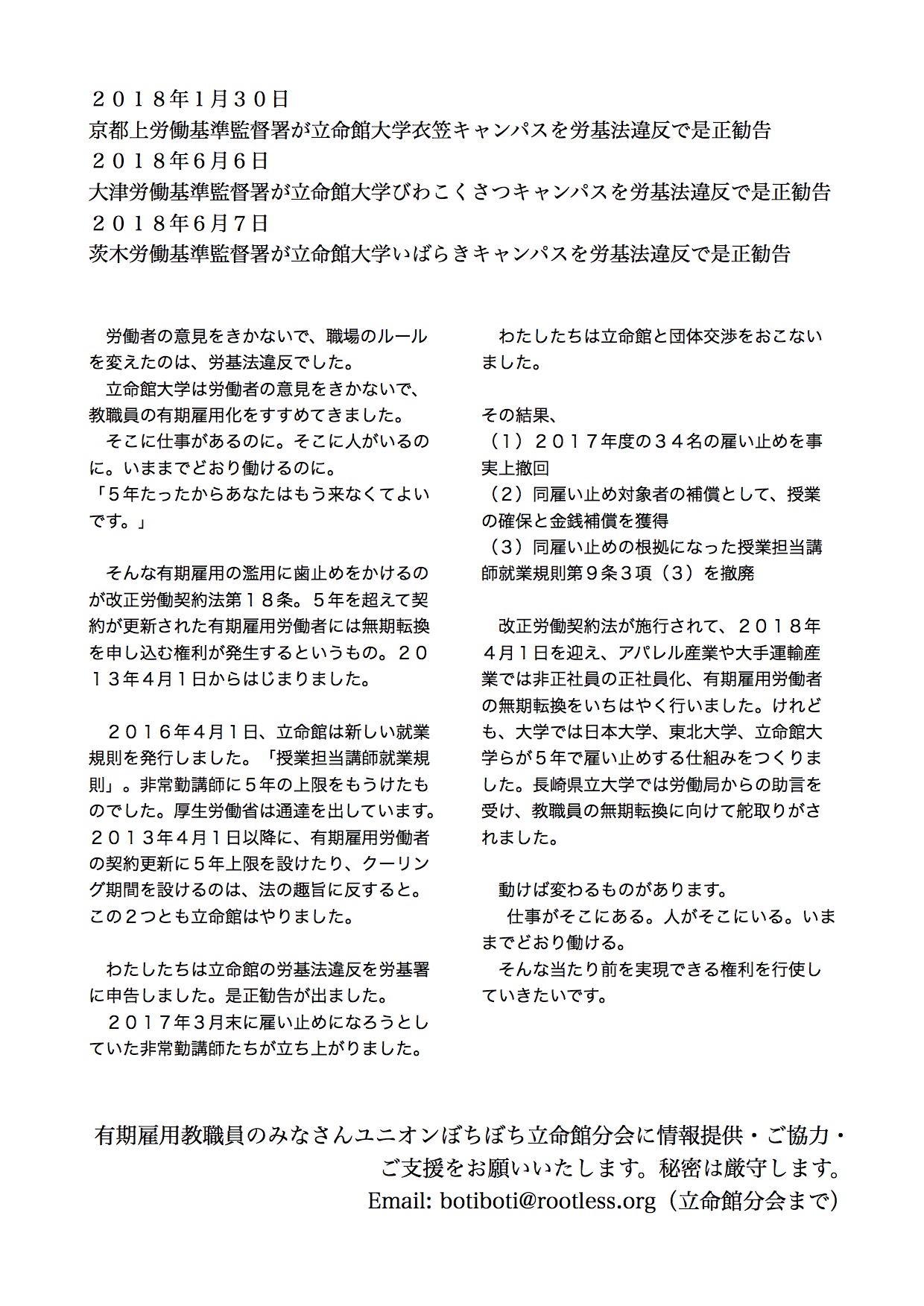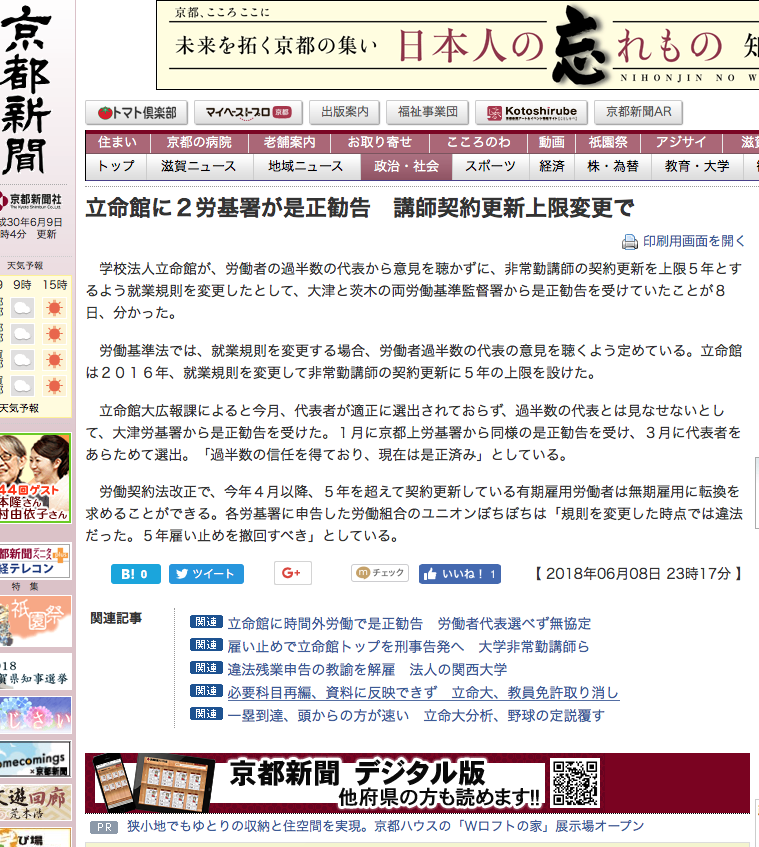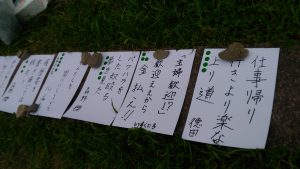みなさん、おはようございます。
6月に入り、2017年度に雇い止めを通告された「授業担当講師」に対して、学校法人立命館より授業の補償などについて書かれたメールが送られています。しかし問題のある文面なので、関西圏大学非常勤講師組合と関西非正規等労働組合で以下のような声明を出しました。
重要なポイントは、2017年度の雇い止め(立命館大学との契約を解除されたこと)は不当であり、大学が講義や金銭的な補償をすると約束していることです。奪われたものを取り戻すためにも、大学に同じようなことを今後させないためにも、ぜひ請求して下さい。
また不安な方は私たち組合に相談してほしいです。実際に組合と一緒に交渉をされている方々がすでにおります。
■関西圏大学非常勤講師組合 http://www.hijokin.org
■関西非正規等労働組合 http://rootless.org/botiboti/
—以下、声明文(転載転送歓迎)
■2017年度に雇い止めを通告された「授業担当講師」に対して、学校法人立命館より送られたメールに関する声明
2018年5月23日に行われた団体交渉の結果、2017年度に雇い止めを通告された「授業担当講師」に対して、
・2018年度後期および2019年度以降の講義を補償すること
・講師側や法人側の事情で講義を保障できない場合は金銭的な補償を行うこと
・希望する者を無期転換すること(特別な事情がない限り、2018年度に申請を受け付けて、19年度から無期雇用で雇うこと)
・その旨を改めてメールで伝えること(内容を伝えやすくするために、送信前に組合と内容を調整すること)
が決まりました。
そして各学部事務室よりメールが当事者の皆さんに送られていると思います。
しかし、このメールに組合の意見は全く反映されておりません。
まず私たちは、人事課より送られてきたメールの文案を最初に見たとき「いつも大変お世話になっております。」という言葉から始まっていることに驚愕し、また怒りを感じました。不当な理由によって職を奪った大学から、奪われた当事者が「いつも大変お世話になっております。」という言葉で始まるメールを送られたらどのような気持ちになるでしょうか?そのようなメールを平然と送る大学に対して、誠意を感じ、安心して補償を求めるということができるでしょうか?
このような無神経な文案に対して、私たち組合は
・まず謝罪から始めること
・補償の内容について説明すること(検討中のことに関しては「検討中」と明記すること)
・経緯など事情を説明する部分は後に書くこと
を求め、文案も作成して返信をしましたが、「急いでいる」という理由によって採用を拒否されました。しかし、当事者の方々にメールが送られたのは、それから10日以上経ってからでした。それだけの時間があれば、メールの内容について調整し改善することができたと考えられますが、送られたメールは文案のままで「いつも大変お世話になっております。」も削除されておりませんでした。
いつになったら、不当な理由で雇い止めをした講師に対して誠実に向き合うのでしょうか?
私たちは、団交における約束を守らないことはもちろん、不当な雇い止めを通告された当事者を幾重にも傷つけ続ける法人の姿勢に対して抗議いたします。
以上